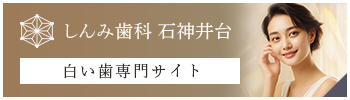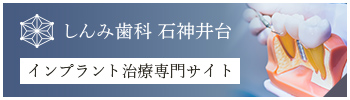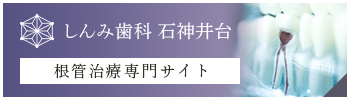ワイヤー矯正は、ブラケットやワイヤーといった金属製の装置を歯に装着して歯を動かしていく治療法ですが、マウスピース矯正は見た目も装置の装着感も大きく異なります。
薄くて透明なマウスピースをつけるだけでどうして歯が動くのか不思議に感じている方も多いことでしょう。
そこで今回は、マウスピース矯正(インビザライン)で歯が動く仕組みとメカニズムについて、練馬区のしんみ歯科石神井台がわかりやすく解説をします。
目次
■マウスピース矯正(インビザライン)で歯が動く仕組み
マウスピース矯正のインビザラインでは、アライナーと呼ばれる樹脂製のマウスピースを使用します。厚みは0.5mm程度しかなく、目立ちにくいことから、どうしてこのようなマウスピースで歯が動くのか疑問に思うお気持ちもよく理解できます。
◎マウスピースの「ズレ」がポイント
マウスピース矯正では、複数枚のマウスピースを使用していきます。標準的なインビザラインの症例なら40~50枚のマウスピースを使用することもあります。
インビザラインのマウスピースは、1枚1枚が少しずつ異なる形になっていて、それらを指定された順番通りに交換することで、歯が少しずつ動かしていきます。
つまり、マウスピース矯正で歯が動く仕組みの肝となるのは、個々のマウスピースの「ズレ」。マウスピース交換するたびに、現在の歯列とも少しズレているため、装着すると相応の圧力がかかるのです。
その結果、歯列全体に圧迫感が生じたり、食事で噛んだ時に痛みを感じたりしますが、3~4日すると症状が落ち着いてきます。これはマウスピースのズレに沿って歯が動いている証でもあるのです。
◎マウスピース矯正で歯が動くメカニズムはとてもシンプル
このように、マウスピース矯正で歯が動く仕組みは、ある意味でワイヤー矯正よりもシンプルです。
なぜならワイヤー矯正は、1歯1歯異なる位置にブラケットを装着し、毎回の通院でワイヤーを細かく曲げたり、新しい装置を追加したりする必要があるからです。
歯列の隙間を埋める時には、金属製のバネや輪っか状のゴムを使うこともあります。
一方、マウスピース矯正(インビザライン)は、マウスピースのズレに合わせて歯が動くだけなので、そのメカニズムも理解しやすいのではないでしょうか。
■インビザラインで歯が動く仕組みはデジタル技術が支えている
マウスピースのズレによって歯が動くなら、誰でも簡単にできるのでは?と感じるかもしれません。しかし、先進の医療設備と、この治療法に関する深い知識や高い技術が必要である点もポイントです。
◎iTero(アイテロ)とクリンチェック
インビザラインで歯を正確に動かすためには、精密な歯型取りが必要です。口腔内スキャナーのiTero(アイテロ)は、スティック状のスキャナーで口腔内をスキャンすることで、患者様の歯並びを立体的に把握することが可能です。
口腔内スキャンしたデータは、クリンチェックと呼ばれるインビザライン専用のシミュレーションソフトに入力すると、コンピューター上での治療計画の立案が可能となります。
◎細かな調整は歯科医師の知識と経験に依存する
クリンチェックを使って治療計画を立てたり、マウスピースを設計したりするためには、歯科医師に高度な知識が求められます。
マウスピース矯正もワイヤー矯正と同じように、細部に調整を加えることで、歯を適切に動かせるからです。
もちろん、マウスピースが出来上がれば、あとは1日20時間以上装着し、1~2週間に1回のペースで交換すれば歯が動いていきますが、そこに至るまでには歯科医師の知識や技術、経験が結集しているといえるのです。
■まとめ
今回は、マウスピース矯正で歯が動く仕組みとメカニズムについて解説をしました。インビザラインに代表されるマウスピース矯正は、1枚1枚のマウスピースのズレを利用して歯が動く仕組みを採用しています。
歯科医師に指示通りにマウスピースを装着・交換していけば、歯は順調に動いていきます。その他、マウスピース矯正のメカニズムやメリット、デメリットなどについて詳しく知りたいという方は、いつでもお気軽に練馬区のしんみ歯科石神井台までご相談ください。