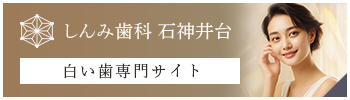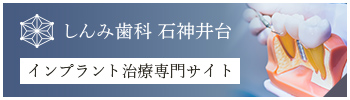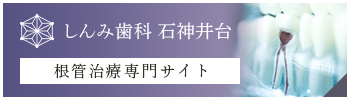インプラント治療を受けたあとに歯ぐきの腫れや膿の排出が見られたら、それは「インプラント周囲炎」という病気かもしれません。
インプラント特有の歯周疾患で、通常の歯周病よりも気をつけなければならない点が多々あります。インプラントの寿命を大きく左右する病気でもあることから、歯ぐきの腫れや膿は見逃さないよう注意しましょう。
今回はそんなインプラント治療後の歯ぐきの腫れや膿の原因、治療する方法などを練馬区のしんみ歯科石神井台がわかりやすく解説をします。
目次
■インプラント治療後の歯ぐきの腫れについて
インプラント治療を受けたあとは、必ず歯ぐきの正常な状態を記憶しておきましょう。歯ぐきというのは、もともと赤みがかっており、腫れていてもあまり気づかない傾向にあります。
また、多くの方は普段から歯ぐきの状態を観察する習慣がないことから、インプラント治療後に何らかの異常が起こっても、見逃すことがとても多いのです。
◎歯ぐきの腫れはインプラント周囲炎の初期症状?
インプラント治療後に歯ぐきが赤く腫れている場合は、インプラント周囲炎の初期症状である可能性が高いです。
インプラント周囲炎とは、歯ぐきとインプラントとの間で歯周病菌が繁殖し、周囲組織に炎症反応を引き起こす病気です。とりわけインプラントと歯ぐきの境目に歯垢や歯石が溜まっている方は要注意。
ちなみに、インプラント周囲炎の初期症状で歯ぐきが腫れている段階は、「インプラント周囲粘膜炎」と呼び、通常の歯周病における「歯肉炎」に当たるため、治療によって改善できる可能性が高いです。
それだけにインプラント治療後の歯ぐきの腫れはできるだけ早めに見つけ、治療を行うことが大切です。
◎インプラント周囲炎とは?
インプラント周囲炎とは、インプラント周囲粘膜炎から進行した歯周疾患で、通常の歯周病の「歯周炎」に当たります。
ただ、インプラントの場合は、周囲の組織に栄養や酸素、免疫細胞を供給する「歯根膜」が存在しておらず、骨とダイレクトに結合していることから、歯周病菌に対する抵抗力が天然歯よりも低いです。
このことからインプラント周囲炎にかかると、歯ぐきや骨の破壊がスピーディーに進み、インプラント体(人工歯根)の脱落が起こりやすくなります。実際、インプラントが寿命を迎える主な原因はインプラント周囲炎となっています。
■インプラント治療後に歯ぐきを押すと痛い
インプラント治療後に歯ぐきが腫れているだけでなく、指で押すと痛い場合は、インプラント周囲炎がやや進行している可能性があります。
これは歯ぐきや顎の骨で強い炎症反応が起こっている証拠で、できるだけ早く歯科を受診してください。この段階であればまだ適切な治療を行うことで、インプラントを失わずに済むかもしれません。
■インプラント治療後に歯ぐきから膿が出てきた
インプラント治療後に歯ぐきから膿が出てきた場合は、インプラント周囲炎の末期へと近づいています。インプラントと歯ぐきとの境目で歯周病菌が異常繁殖することで、膿の排出が起こります。
インプラント周囲炎がここまで進行すると、対症療法によって膿の排出を抑えることはできるかもしれませんが、完治させることは難しくなります。それだけにインプラント治療後は歯ぐきから膿が出る前に、インプラント周囲炎の治療を受けたいところです。
もちろん、インプラント周囲炎によって歯ぐきから膿が出ても完治することもありますし、早期の治療が必要であることに変わりはないため、できるだけ早く歯科を受診してください。
■インプラント治療の歯ぐきの腫れや膿の治療法
インプラント周囲炎の治療法は、一般的な歯周病治療とほとんど同じです。軽度であれば、クリーニングやスケーリング(歯石除去)を行い、歯周病菌の数を減らします。
必要に応じて抗菌薬による洗浄や内科的な治療も行われます。重症度の高い症例に対しては、歯ぐきをメスで切開してインプラント体表面の汚れを取り除いたり、吸収した骨を再生させたりする治療が行われます。
インプラント周囲炎を完治させることが難しいと診断した症例では、インプラント体の撤去が必要となります。インプラント体を撤去したあとは、骨の再生をおこなってから再埋入したり、ブリッジや入れ歯といった従来法で補綴治療をやり直したりします。
■まとめ
今回は、インプラント治療後に歯ぐきの腫れや膿が認められた場合に考えられる原因や治療法について解説しました。インプラントを埋め込んだ部位の歯ぐきが腫れたり、膿が出た場合は「インプラント周囲炎」が疑われますので、歯科を受診するようにしましょう。
インプラント周囲炎でも早期に治療できれば、完治が望めますが、対処が遅れるとインプラントそのものを撤去せざるをえなくなります。
せっかく治療したインプラントを長く使い続けるためにも、正しいセルフケアや歯科医院でのメンテナンスを行い、早期発見・早期治療に努めましょう。